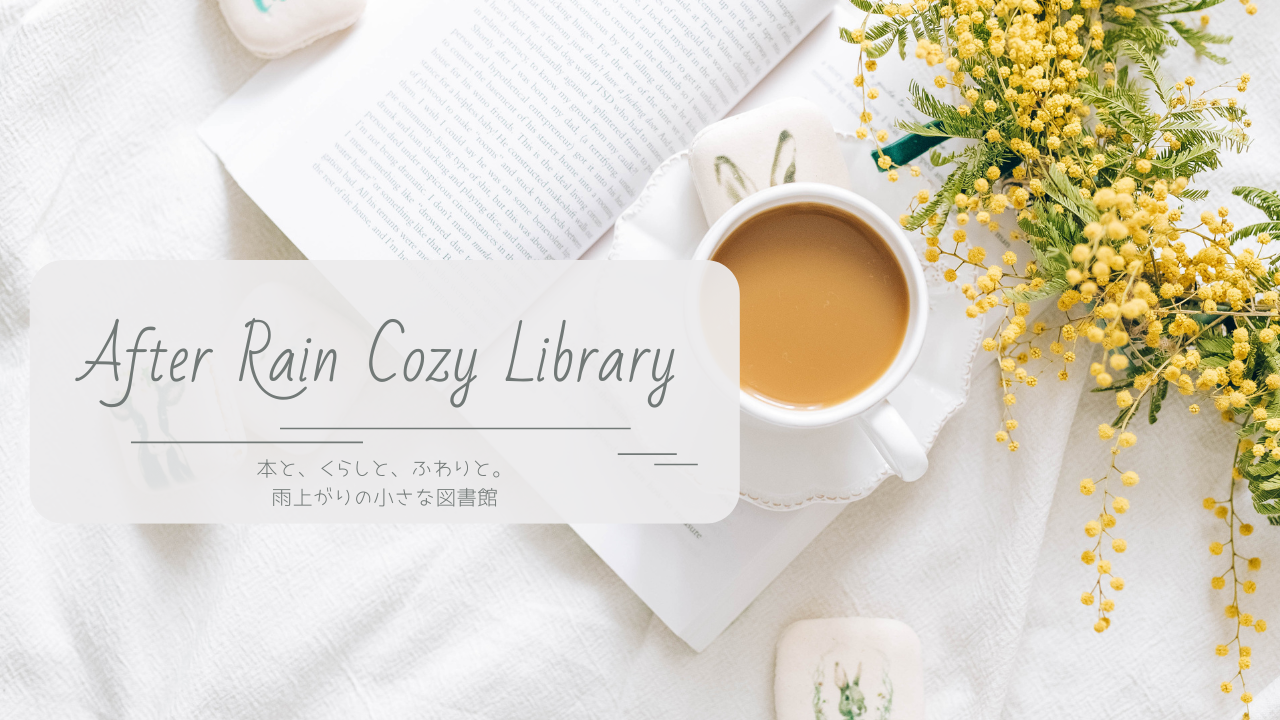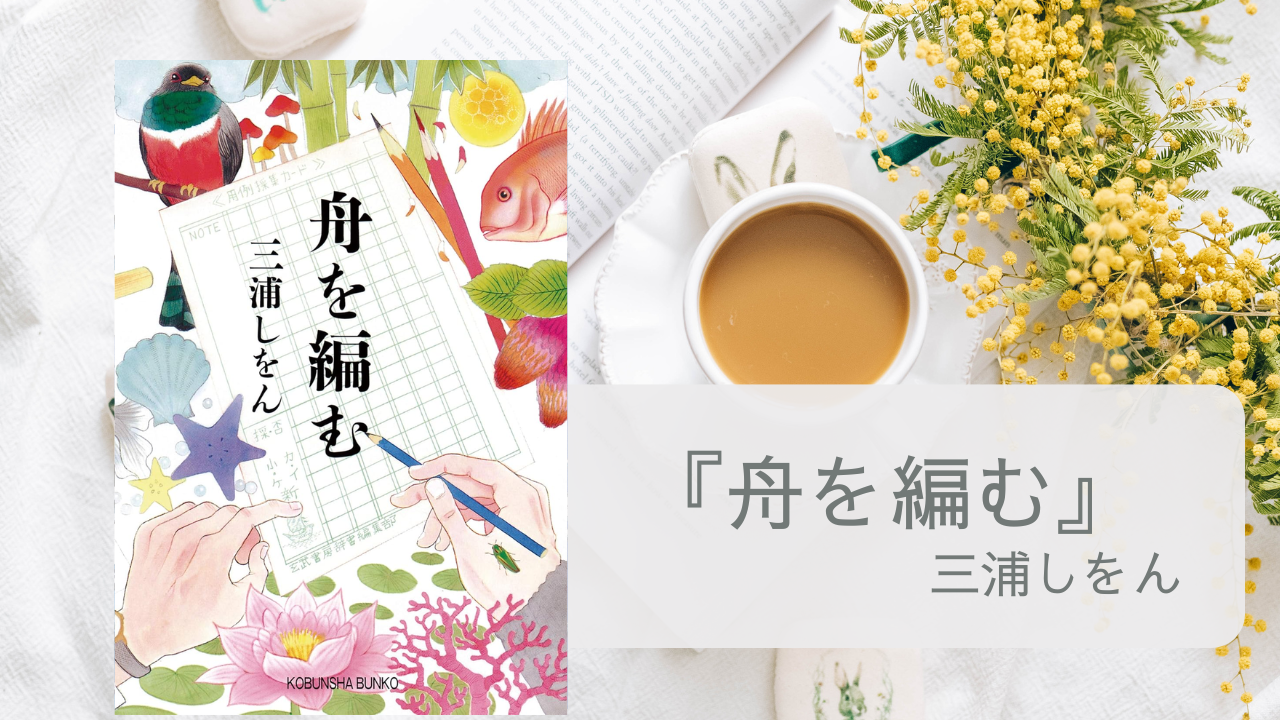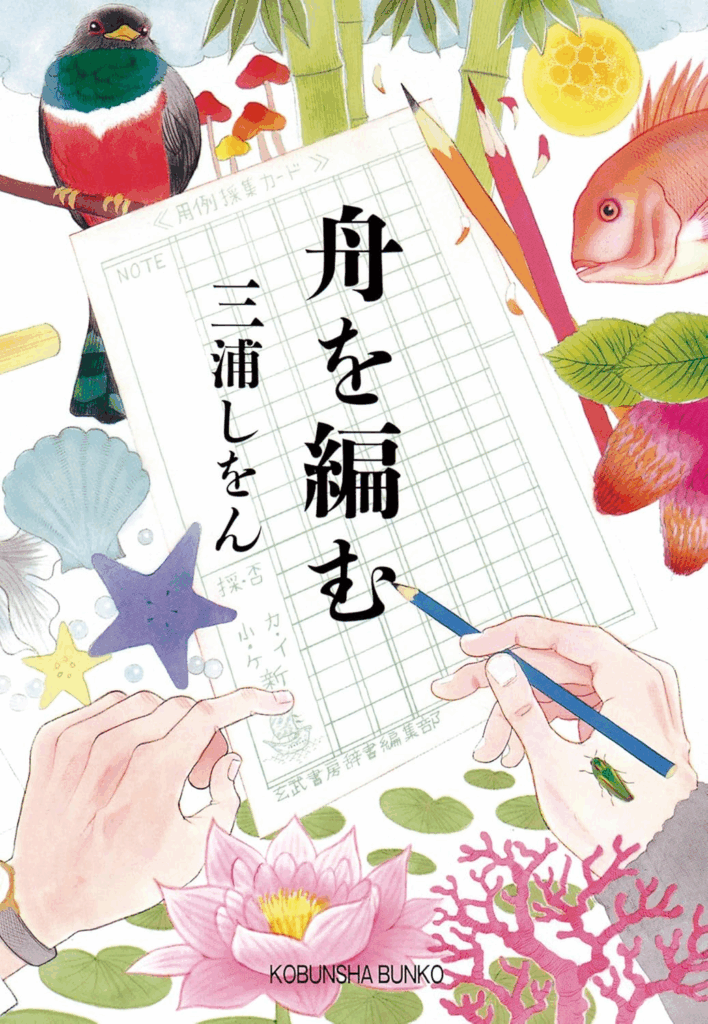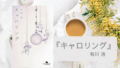※前ブログ「Departure’s borderline」からの転記です。
2018年1月12日に、実に十年ぶりとなる『広辞苑』の改定版、第七版が出ました。
物書きを生業としている端くれである以上、辞書は生活に欠かせないものです。今は、スマホが発達してしまって、紙の辞書をひくことってあまりないのだけれど、頼まれてエッセイを書く時などは必ず紙の辞書を傍らに原稿を進めます。
新しい広辞苑には、「アプリ」や「小悪魔」などが追加されたそうで。
「LGBT」の誤表現発覚のニュースはまだ記憶に新しいところでしょう。
さて、『広辞苑』が出てから、三浦しをん先生による『舟を編む』を読み直していました。
これ、光文社から出てるんですよね。最近の光文社文庫だと、売り上げはだいぶ上位に食い込むのではないでしょうか。
作品じたいは2016年秋クールで、フジテレビ”ノイタミナ”枠でアニメ化されています。ノイタミナアニメって、毎回クオリティ万全だからついつい見ちゃう。
出版社の営業部員・馬締光也(まじめみつや)は、言葉への鋭いセンスを買われ、辞書編集部に引き抜かれた。新しい辞書「大渡海(だいとかい)」の完成に向け、彼と編集部の面々の長い長い旅が始まる。定年間近のベテラン編集者。日本語研究に人生を捧げる老学者。辞書作りに情熱を持ち始める同僚たち。そして馬締がついに出会った運命の女性。不器用な人々の思いが胸を打つ本屋大賞受賞作! 馬締の恋文全文(?)収録!
Amazonより
アニメでは、玄武書房は「あ、これ新潮社!?」みたいな社屋が描かれている気がします。
新しい辞書は売れない
まず前提として、辞書を出している出版社って、意外と少なく、辞書編集部がある会社も限られているんですよね。しかも、新しい辞書は確かに売れません。『広辞苑』とか、『大辞林』とか、名前のある辞書はコンスタントに売れ続けますが、作中で作っていく辞書はまったく新しい辞書。編纂しようと思っている編集者が、どれほど日本語に対して熱い思いを持っているかがわかります(たいていは企画を出したところで通らない)。
作中で主人公である馬締たちが作っていく『大渡海』は、1932年~1935年刊行の『大言海』(冨山房)が語源かなと勝手に思っています。『大言海』も、『大渡海』と同じく中型の国語辞典でした。
もう80年近く前のものですから、私は実際に手にとったことはありませんが。
とにかく日本語が美しい
三浦しをん先生の作品、ほぼすべてに言えることではあるのですが、この作品は特に日本語がキレイだと思います。さすが辞書編集の物語としかいいようがないです。
例えば、
「あの頃の先生はもっとこう、茂らせてらしたもんだが」
「荒木くんも、ずいぶんと頭に霜をいただくようになったではないですか。」
という、『大渡海』に関わる2人のやりとりがあります。もちろん、日本語としてそのまますんなり理解ができる表現ではあると思います。白髪頭のことを”霜をいただく”と表現しているわけですね。
ただ、日常生活の中で、ここまできれいな日本語を使った会話をしている大人って、そうそう居ないと思います。とっさの会話で”霜をいただく”という表現が出てくる、三浦しをん先生の日本語力と語彙力に乾杯。
生きることに不器用な男が成長する
この作品の主人公、馬締は、非常に生きるのが不器用だと思います。たぶん10人中9人が「どんくさい奴だ」とか言うんじゃないかな。そんな馬締が、”辞書”を通して成長する、というところが作品の軸です。彼は辞書編集部に十数年関わるうちに、主任になり、部長になり、責任を持つようになります。不器用な彼なりに、その責任を果たそうと努力し、成長していく姿が見ていて清々しいです。
また、そんな不器用な彼を支えていく辞書編集部の人々、のちに結婚相手を見つけることになる下宿での暮らし。彼を取り巻く環境も、非常に温かい。生きることに不器用な男が、生きやすい環境が描かれているというか。そこはヌルいなと思ってしまったけれど。
まとめ
とにかく、日本語が好きならば読んで損はない作品なんじゃないかなと思います。お仕事小説としてのクオリティも非常に高い。アニメから入ったとしても、アニメそのものがとても原作に忠実なのでそのまますんなり読める本なのかなと。
広辞苑は新規辞書ではなく、辞書改定だったわけだけれど、大編成の辞書だからこそもっと多くの人がかかわっているのだろうと思います。これからも日本語はどんどん増えていくのですから、もう一度、正しい日本語の意味を知る必要ってあるんじゃないかな。そのためにも、辞書、買おう(宣伝じゃない)。